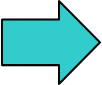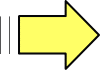片山会計事務所グループ
ホームページへようこそ


| 税務調査とは? |
| このページで触れる【税務調査】ですが、あくまで国税局や税務署が行うものに限定をして記載しております。 もちろん都道府県や市町村も税務調査を行うことはあるのでしょうが、ここでは触れておりません事をご承知ください。 また国税局や税務署が滞納処分のために行う調査についても触れておりません。 |
税務調査は申告後に行われます。 所得税・法人税・消費税といった税金は、まず納税者側が自ら計算して提出された申告書により税額が確定いたします。これを申告納税制度と言います。 そして税務調査はこの申告が済んだ後に行われます。 つまり税務官公庁(国税局や税務署など)が、納税者が提出した申告書の真否を確認するために行われるものです。 申告納税制度の維持のためにはこの税務調査も必要不可欠のものです。 昭和40年代辺りまでは、納税者が自らの申告書を提出する前、つまり税額が確定する前に事前調査と呼ばれる税務調査が行われていた事もあったらしいですが、現在は税務調査は原則は申告書による税額確定の後に行われるのが一般的です。 但し納税者側が自ら申告書を提出しない場合に調査が行われる事はありますが、あくまでその申告書の法定申告期限が済んだ後の実施となります。 |
| 税務調査の99%以上は任意調査です |
| 税務調査はまず大きく分けて強制調査と任意調査 とに区分されます |
| 強制調査(マルサ)とは 国税局の査察部(通称マルサ)が実施するもので、脱税の容疑のある納税者に対して行われるものです。 裁判所の捜査令状を持って突然に調査に来ますし、納税者側の都合云々で調査の拒否は出来ません。また家宅捜査を受けて証拠書類等の差押えも受けます。 伊丹十三の映画【マルサの女】をご覧になられた方はご承知と存じます。 宮本信子の若かりし頃の映画です。 強制調査(マルサ)を受けた場合は原則的に脱税していた税金の追徴に刑事罰も加わり実刑になる場合もあります。 一年間でマルサを受ける対象者は全国で2~300件程度らしく、普通の企業にはまず縁が無いでしょう。 あくまで悪質な脱税容疑のある企業等に対して行われる調査です。 |
| 任意調査とは 国税局や税務署が実施する税務調査のほとんどがこの任意調査です。 裁判所の捜査令状により調査が行われるマルサとは違い、あくまで納税者側の任意での調査承諾が前提となる調査ですが、但し理由無しに拒むと罰則もあります。 |


| 憲法と課税の要件について |
| まず最初に日本国憲法の条文を引用させていただきました。 ご存じの通り憲法は最高法規であり、更に行政機関で働く公務員には憲法の遵守義務も規定されております(99条)。 税務調査を行う調査官達も当然にこの憲法の遵守が義務づけられているのですが、実際の税務調査に於いては法律に従わない課税が強要される場合もあり、改めて憲法の条文を再確認する意味でここに引用させていただいたものです。 |
| 日本国憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う |
| これは「租税法律主義」と言われる憲法の規定条文であり、勤労と教育と共に国民の三大義務である納税義務を規定したものです。 納税が国民の義務である事は皆様ご承知の通りなのですが、大事なのは「法律の定めるところにより」の部分です。 納税が国民の財産権に踏み入るものである以上、その根拠は必ず法律によらなければならないという当たり前の規定であり、別な表現をすれば法律に基づかなければ納税の義務を負わないという規定です。 |
| 日本国憲法84条 あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする |
| 調査官が税務調査等で企業に新たな課税を行う場合には、必ずその課税が法律の定めによるものかどうかが問題となります。 この憲法84条の規定を課税要件法定主義と呼んでいます。 |
| 税務調査での課税は必ずしもこの課税要件法定主義を充たしてはいません。 つまり課税要件である法律根拠が存在せず、憲法規定上は課税できないものを、調査官達は厳しい調査件数ノルマで無理な課税を行っているものが実際の税務調査ではかなり含まれています。 これは課税庁側の更正決定処分として行われる課税ではなく納税者が修正申告書の提出といった形で「自主的」に申告を済ませている以上は決して表には出てきません。 |
| 税務調査では法的根拠より「通達」で課税判断することが一般的 |
| 課税庁は法律よりも「通達」で課税を行う事が一般的です。 通達とは 国家行政組織法14条2項により大臣が下級庁に対して発するもので、問題になるのは法律の解釈を大臣または長官が決めてしまう解釈通達です。 解釈通達は、例えば国税庁長官が発したものでしたら、国税庁の下級庁である国税局や税務署員は必ずこの解釈に拘束されますが、下級庁の職員以外の一般国民はその解釈に縛られる事はなく自由な租税解釈権を有しています。 通達とは国民に選ばれた国会議員により国会で審議されて可決された法律ではなく、大臣または長官の判断だけで下級庁に指示されるものですから、この解釈で課税を行う事は明らかに課税要件法定主義に反しています。 (つまり自社の社内規則を社外の人達にも守らせようとする様なもの) 国税不服審判所は国税庁の下級庁ですが、国税通則法99条により通達に拘束されることはありません。しかし通達と異なる解釈を行おうとする場合には事前に国税庁長官に通知をしなければならない事になっています。 |
| 修正申告書の提出を行った場合はどんな課税も合法となり問題化はしない |
| 更に通達でもなく解説書の一文を根拠にしたり、或いは過去の前例だけで課税をしたりという乱暴なものも見受けられます。 下手すれば調査官個人の主観的な判断だけでも、もし納税者が修正申告書を提出してしまえば課税は合法となり問題化することはありません。 |
| 税務調査を受けた際には、課税庁側が示した課税案に安易に修正申告書を提出するのではなく、必ずその課税案が課税要件を法的に満たしているかどうかの検討を行う事が重要です。 課税庁からの更正決定処分を受けて争う事で少しでも憲法の精神が生きる課税になればと思います。 |
| 税理士として猛省しなければならないのは安易な修正申告書の提出 |
| この様な課税要件法定主義に反した課税が税務調査で横行している理由の一つには、調査を行う調査官達の厳しいノルマ(後で触れます)もありますが、我々税理士の対応にもかなり問題があるのだと思っております。 税理士は税務調査の立会権を持っており、その際の税理士の対応が依頼人である納税者の税負担に大きな影響を与えます。 我々税理士が調査官の課税案を安易に認めて修正申告書を「自主的」に提出をして調査を終わらせるといった対応を繰り返している限り、法的根拠の無い課税は無くならないでしょうし、納税者の皆様に余計な税負担を発生させるだけのことです。 残念ながら調査官のいいなりの課税案で修正申告書を「自主的」に提出する税理士はかなり多いらしいです。 税理士の中では税務署OBの税理士も多く、調査官の課税案に面と向かって対決するといった骨のある方は少ないようです。 |
| 国が行う調査なのに違法なんてことがあるはずが無いでしょ? これは調査を受けることが心配で事前に電話相談されたある方から言われたことです。 (税理士の関与がない方で、初めて受ける調査が心配だったそうです)。 そして私が事前に用意する資料や調査官との問答の件などをアドバイスした後に、もしかしたら違法な調査の可能性もありえますよ、とお話しした際に聞かれたことです。 違法というとどうしても犯罪的なことを連想してしまうのですが、さすがに税務調査でその様なことは私だって想定をしておりません。 ただ法的根拠も無い課税案を強要される可能性もありますよとお話しした訳ですが誤解を招いたようです。 この方は遠方の方で、電話でアドバイスを頼まれただけで関与も立会もしておりませんし、その後の調査の結果がどうなったかも知りません。。 |
| 実際に明らかな違法調査は存在をしています |
| 後で触れますが、「現況調査」などは私は明らかな違法調査だと思っております。 国税通則法が平成25年に改正され、それ以降はあまり目立たなくなった様ですが、後で詳しく書きました「リョーチョー調査」などは違法調査そのものでしょう。 |

| 基本的人権と税務調査 |
| 憲法11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる 憲法97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである |
| 税務調査では、原則は国民に受忍義務があります。 つまり正当な理由が無い限りは拒否する事ができず、いくら「任意調査」であっても実際にはこの様に「間接強制」といった形で否応なしに調査を受ける事となります。 税務調査であっても憲法に保障されている基本的人権が侵害される事はありません。 しかし残念ながら税務調査と基本的人権との狭間では色々な問題点もある様です。 |
| そもそも税務調査では憲法30条(納税の義務)により国民の財産を調べて納税額の正否を調べるものですから、29条(財産権)のある程度の制約はやむを得ないのではないかと思っております。 プライバシーにまで踏み込む様な調査が13条の幸福追求権を侵害するかどうかは判断が分かれるところですが、少なくとも調査が31条(適正手続の保障)により法に基づいて行われているものならば、「公共の福祉」により許容範囲になるのかも知れません。 35条(住居の不可侵)についても、調査という目的のためだったら、ある程度までは仕方がないものと思われますが、実際にはこの後でも記載する様な、違法としか思えない現況調査が日常的に行われております。 納税者が自らの意思で加入している団体組織を課税庁が敵視し、その団体加入者に対して見せしめとも思えるような税務調査を行っている事実は明らかに19条(思想・良心の自由)や21条(結社の自由)を侵害している行為でしょう。当然に法の下の平等を定めた14条にも違反していると思います。 税務調査を少し離れますが、滞納している税金に無理な差押えをして生活困窮状態に追い込んでしまう行為(地方税に多い)は25条(生存権)を侵害しています。 この様に、人権と調査との間には色々と摩擦があるようです。 税務調査は国の歳入確保という「公益」と国民の基本的人権との狭間で行われます。 税務行政というのは、全てが法律に基づいて行われている訳ではなく、中には過去からの慣例や慣習だけによるものだったり、或いはお役所が法律を勝手に自分成りに解釈をした内容で行われる場合もあります。 特に平成25年まで全く根拠法が無かった税務調査手続などは正に無法地帯となっておりましたし、国民の人権が大きく侵害されていた状態でした。 特にリョーチョー調査が代表的なものでした。 (リョーチョー調査は後で詳しく書きます) |


| 税務調査の法的根拠と開始手続 |
| 調査権(質問検査権)は国税通則法の規定によっています |
| 税務官公庁(国税局や税務署等)が税務調査を実施する際の法的根拠である質問検査権は国税通則法に規定がされています。 以前は法人税法・所得税法・消費税法といった各税法にそれぞれその旨の規定があったのですが、平成23年の改正で、国税通則法第74条の2以降に各税目の質問検査権が追加で規定され、全ての質問検査権が国税通則法に統合されました。 質問検査の対象は会社代表者や経理担当者だけに限定している訳ではなく、ご家族や従業員にも及ぶとされています。 そしてこの質問検査に対しては正当な理由無しに拒否はできません。 しかし最高裁昭和48年7月10日小法廷の判例によれば、拒否しても物理的な強制は行えない、とされています。 |
| 法律で定められた税務調査手続とは |
| 「国税庁、国税局、若しくは税務署の当該職員は」 「税の調査について必要のあるとき」 「質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、」 「当該物件の提示若しくは提出を求めることができる」 国税通則法第74条の2ではこの様な文言で所得税・法人税・消費税の質問検査権が規定されています。 また同法74条の3では相続税・贈与税、そして74条の4で酒税に関する規定が定められており、全て同じ様に質問検査を行うことができる職員とその条件が定められています。 質問検査は「調査の必要があるとき」に行うことができる権利です。そしてその必要性は調査官の独自の判断ではなく、あくまで客観的に必要がある場合にのみ行えます。 調査官の中には税務調査では何でも質問できると勘違いされている方もいるようです。プライベートな質問にはお答えする必要はありません 更に質問検査を行う際には、国税通則法第74条の9の規定により、事前に調査の対象となる納税者に対してその旨の通知、つまり事前通知を行わなければなりません。 |
| 事前通知で通知される事項 |
| 事前通知では、課税庁は以下11項目を通知しなければなりません。 1 実地調査を行う旨の通知 2 実地調査を開始する日時 3 実地調査を行う場所 4 実地調査の目的 5 調査の目的となる税目 6 調査の対象期間 7 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 8 調査の対象となる納税者の住所氏名 9 調査を行う調査官の氏名とその所属 10 調査の日時と場所は変更も可能である旨の伝達 11 4~7で通知されなかった事項についても改めて調査を行う可能性 この様な事項を何故か電話で通知をしてきます。 本来は文書で通知を出せば課税庁側も楽なのでしょうが、課税庁は何故か絶対に文書を出さず電話で通知をしてきます。 そのため通知の内容で「言った、言わない(聞いていない)」といった問題も頻発する事になります。 もし通知漏れがあった場合、法的にはその調査は違法となるはずですが、通知自体が証拠の残る文書ではなく電話のため、通知漏れの立証は現実的には不可能です。 よって中には後々のトラブルを考えて録音される方もいるようです。 また、4の「実地調査の目的」ですが、法の趣旨からして本来は「調査の理由」を示すべきだと思うのですが、課税庁は絶対にその理由を示しません。 なお先進国ではほとんど税務調査は文書で事前通知がされており、証拠が残らない電話でしか通知を行わない日本の遅れた体質には問題があります。 |
| 納税者に対して税務調査の事前通知を行うのは税務署長 |
| 国税通則法第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)の規定では、税務調査の事前通知を行うのは「税務署長等」と明確に定められています。 そしてこの「税務署長等」とは国税庁長官と国税局長、税務署長と税関長であると法律で明確に限定をされており、つまり税務署が納税者の調査を行う際には、法的には税務署長自身がその旨を通知しなければならないと規定をされている訳です。 しかし実際には税務署長が電話を掛けてくるなどといった例はまず無く、通常は税務職員などが電話をしてくる訳ですが、これはやはり法律に基づいて行う行政としては異様なことだと思われます。 元々、税務調査の事前通知規定は法律上は存在していませんでした。 事前通知だけではなく税務調査の手続に関する法律がそもそも存在しておらず、それまでは国税局や税務署等が勝手に法律の解釈や判断をして、謂わば好き放題の税務調査を行ってきたという恥ずかしい歴史的事実がありました。 自民党が野党に転落した時に初めて税務調査の規定が整備され、その際にこの事前通知の規定が新たに設けられた訳ですが、当初案では諸外国の様に税務署長名の文書で送付して調査の事前通知を行うはずだったものを、その後の自民党の政権復帰や国税庁側の強い希望もあり、この文書通知の部分が撤廃されて規定が骨抜きとされたものと聞いております。 税務署長は部下の職員に委任をして事前通知を電話で行っている訳だから、仮に事前通知を税務署長自身が行わなくても全く問題が無い、というのは国税庁の言い分です。 しかし法律上は税務署長自身が行うことと税務署長の指示や命令により部下の職員が行うことは明確に区分がされています。 例えば、上に挙げた税務調査の質問検査権を規定した国税通則法第74条の2をご覧いただくと分かります様に、部下の職員が行えるものは「当該職員」と明確に書かれています。事前通知を部下の職員が行うのだったら、国税通則法第74条の9にも「当該職員」といったことが書かれている必要があります。 質問検査権規定では「当該職員」と限定をして税務署長以外の一般税務職員に検査権限を与えているのに、その一方では事前通知ができる権限を持つ税務署長に一般職員も含めてしまうといった強引な法律の解釈には少し首を傾げざるを得ません。国税庁の言い分は素人が見ても法文の整合性が取れず、下手な言い訳にしか感じません。 |
| 事前通知を行わない場合とは |
| 税務調査を行う際には、事前に納税者にその旨を通知するというのは当たり前のようにも感じますが、残念ながら例外規定もあります。 例外規定は国税通則法第74条の10に規定されており、事前通知を行うことで納税者が帳簿書類を破棄・隠匿・偽造等の怖れがある場合には例外的に事前通知無しに税務調査を行えるというもので、その事例の例示は国税庁の通達に記載されています。 大事な事は、これらの怖れがある事が合理的に推認される、事が条件であり、課税庁側だけの判断で勝手に「推認」をする訳ではありません。 合理的に推認というのは、「誰が見てもそう判断するだろう」という程度の前提条件が必要なのであり、形容を替えれば、納税者側にもある程度やましい気持ちがあって身の覚えがある方でないと適用されないのではと思われます。 |
| 改正国税通則法は2013年(平成25年)1月から適用となりました。そしてこの改正前は、先にも書いた様に税務調査手続を含めた事前通知に対する法的根拠は存在していませんでした。そのため税務署や国税局が調査を実施する際、事前通知無しに税務調査を行うといった事が頻発しており、人権上様々な問題を起こしていました。 小売店や飲食店の様な現金商売の方などは、いきなり税務署の訪問を受けて嫌々ながら調査に応じざるを得なかった方々も多いのではと思いますが、平成25年以降はこの様な調査には制約が掛かり、法的に上記第74条10の要件を充たさない限りはできなくなったという事です。 「現金商売だから」 「過去の調査で売上を抜いていた履歴があった」 「脱税をしているらしいとのタレコミがあった」 この程度の理由だけでは、「合理的に推認」に当たらない事は国税庁も認めています。 ※ 平成24年9月 国税庁課税総括課「事前通知の要否の判断について」より 後で触れる「リョーチョー調査」にも出てきますが、国税局や税務署は税務調査での実績と効率を上げるためにはなるだけ事前通知は行いたくはないらしく、「合理的に推認」の根拠を絶対に明かそうとしません。「推認」の根拠を秘匿するのだったら事前通知の義務規定は完全に骨抜きにされますし、税務官公庁が好き放題にできることになります。 |
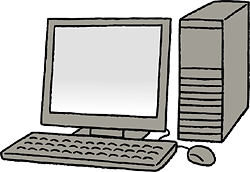
| 調査の実施と問題点 |
| 調査実施日時は税務署等が一方的に指定はできません(納税者都合にも配慮) |
| 税務調査の事前通知は、通常は関与税理士さんに対して電話で行われます。そして税理士さんからの連絡を受けて日程調整等を行い調査の日時が決まる訳ですが、その日程調整等は全て税理士さんと税務署との間で行われますから、納税者ご自身が直接税務職員と電話応対する機会はあまり無いかと思われます。 しかし関与税理士さんが居ない場合には納税者の皆様が直接税務署等と応対することとなりますので、まず法定通知事項の11項目が全て通知されたかどうかは必ずチェックしてください。 そして調査の日時ですが、税務署が一方的に強引に指定してくることがありますが、必ずしも税務署側の希望に添う必要はありませんからご自身の都合の良い日時を主張して決める様にしてください。 調査実施日時は、通常は事前通知のあった日から最低一週間以上後の日になるはずです。事前通知でいきなり明日とか明後日とか指定されても、それは納税者側の都合を無視した一方的なものですから断る様にしてください。 但し忙しいから半年先にしろとか一年後に受けるとかの返事は絶対にお止めください。こういう返答だと調査拒否という扱いになり不利益となりますので、事前通知があった時にはできるだけ誠意を持って日程の調整をお願いいたします。 |
| 調査ではプライベートな部分も調査されることがあります |
| さあ、調査のスタートですが、まず最初は経営者や経理責任者からの聞き取りから始まります。これを課税庁内では「事業内容の聴取」と称しており、業務の具体的な内容や主な取引先、取引金融機関や取り扱い商品等々を聴き取り、これにより調査官は調査のポイントを絞ります。 第二段階としていよいよ調査が本格的にスタートします。総勘定元帳や出納帳等の各種補助簿、請求書や領収書といった証憑類(課税庁側では原始記録と呼んでいます)や預金通帳等を確認します。 調査で確認される書類は、この外にも単なる電話メモやFAXの受信記録、更にはパソコン内に保存されたデータや電子メールにまで及ぶ場合もあります。調査の事前通知段階で調査する帳簿書類を特定して通知をしているにも関わらず、実際の調査では様々な書類に調査官の手が伸びる事となります。よってプライバシーの侵害と取られる行為も調査の中では必然的に起こってきます。 <国税庁の公式見解> 納税者は任意で選択したものを提示すれば足りるというものではなく、仕事に関係があるか無関係であるかは調査官が確認して判断する つまり納税者側が「調査には無関係の書類」と判断しても、調査官がその書類が本当に調査に無関係かどうかを確認するといった見解であり、これではプライバシー侵害問題が出るのは当たり前です。 |
| 調査の対象となる年度は一般的には3年(期)分で対象税目も事前に通知されます |
| 税務調査の事前通知の段階で、調査の対象となる年度(年分)は法定通知事項ですから必ず連絡をしてきます。 法人税でも所得税でも直近の申告から3期(年)分というのが一般的でしたが、最近は5期分も遡って調査をする例も増えている様です。 また、まだ申告を済ませていない年度、つまり現時点の調査(進行年度といいます)が行われることもあります。例えば前日や前々日のレジペーパーを確認したり調査日時点での在庫を確認したり、またその日の現金の残高を確認したり(現金監査)する場合もあります。 調査対象税目も事前通知で通知されるはずです。法人税の調査の場合は法人税と消費税、更に従業員の給料に対する源泉所得税といった税目が調査の対象として通知がされているはずですし、必ず消費税と源泉所得税がセットで調べられます。時には印紙税の調査なども行われる場合もあります。 |
| 現況調査は違法な調査です |
| 家宅捜査そのものの「現況調査」は数多くの調査のトラブルを招いています |
| 調査官によっては、会社側が調査官の求めに応じて提示しようとする請求書領収書等の原始記録類や各種証憑等の提出に待ちきれないのか、自ら立ち上がってその保管場所を実地で確認しようとする場合があります。 これは単なる保管場所の確認という意味ではなく、その周辺にどの様な書類が保管されているのかを直接調べるがためのものであり、課税庁側ではこれを「現況調査」と称して内部的に推奨してきた調査法です。 具体的には、 調査官「●●の書類はどこに置いてありますか?」 会社側「××に置いてありますので今すぐ持ってきます」 調査官「一緒に行きますから保管場所を見せてください」 といってその場所に案内させ、 調査官「この中には何が保管されていますか」 会社側「この中には調査に関係する物は何も入っていません」 調査官「関係あるか無関係かは私が確認しますから出してください」 正に警察の家宅捜査そのものです。 税務調査での調査官は直接手で机やロッカーを開けたりする事は禁じられており、必ず会社側に言葉巧みに開けさせようとします。 税務署ではこの現況調査を通称「ガサ入れ」とも呼んでいます。 会社の事務室内だけではなく、プライバシー空間であるはずの経営者の居宅内、場合によっては寝室内まで調査を受けた事例もあり、このあまりにも酷い調査法にはトラブルも続出しており裁判沙汰になった例もいくつもあります。 |
| 現況調査は絶対に承諾しないで明確に断ってください |
| 現況調査であってもこれは強制調査ではなくあくまで任意調査でしかありません。 任意調査というのは納税者の同意が前提となっており、納税者側がこの調査法に同意をしなければ現況調査もできません。 調査が終わった後になってからプライバシー侵害だとか裁判沙汰だとかと怒っても仕方がないので、その場でこの様な調査に対してはハッキリと拒否の意思を示す必要があります。 調査官「この中には何が保管されていますか」 会社側「この中には調査に関係する物は何も入っていません」 調査官「関係あるか無関係かは私が確認しますから出してください」 会社側「プライバシーのものですからお断りいたします」 この様に明確に拒否をしないと、調査官は黙示の承諾、つまり納税者から明確な拒否が無かったから承諾があったものだと勝手な判断をされてしまいます。 本来は納税者からの明示の承諾があって初めて調査ができるのですが、課税庁側は明確な拒否が無いイコール同意があったものと勝手な判断をしてしまいますので注意が必要です。 必ず「お断りします」と明確に拒否の意思を明確に伝えてください。 拒否の理由は言う必要はありません。 調査官「何故この中を見せていただけないのですか?。」 会社側「調査に関係がないプライバシーのものだからです」 調査官「この中には脱税の証拠があると私は判断しますよ」 会社側「ご判断は勝手ですけど、でもこの調査は任意調査ではなかったのでしょうか」 調査官「・・・」 会社側「この中をどうしてもご確認なさるのでしたら捜査令状をお持ちください」 これは実際にあったやり取りです。 この様にハッキリと拒否をしないと後々で後悔する事にもなります。 上にも書きましたが、調査官には直接机の引き出しを開けたり現金に触れる事は固く禁じられており、もし調査官が納税者側の制止を振り切って勝手に中を確認する様な行為があったとしたら事件となってしまいます。 |
| 現況調査を断っても何ら支障はありません |
| マルサの調査の様な強制調査ならば裁判所の捜査令状がありますから、担当調査官は裁判所が認めた場所にある全ての机やロッカーなども自由に開けて中を確認できますし差押えも可能です。しかし任意調査では全て納税者側の明確な承諾が必要であり、納税者が拒否した調査は絶対に行えません。 現況調査を断った時に、調査官によっては、だったら裁判所の令状を取ると脅す人もいたらしいですが心配はいりません。堂々と拒否をしてください。 捜査令状は脱税という犯罪行為の疑いが濃い嫌疑者だと裁判所が認めた場合にのみ発行されますので、単なる現況調査に応じないとか机の中を見せないから脱税の疑いがある等々の理由で発行される事はあり得ません。 捜査令状の請求には課税庁はもっと具体的事実を積み重ねて脱税の証拠を立証する必要がありますし、請求できるのは国税局の査察部だけです。 会社側「税務調査には全面的に協力いたしますが、あくまで任意調査の上での事です」 調査官「・・・」 会社側「まるで家宅捜査の様な調査のやり方には当社としても協力は出来かねます」 現況調査を断っても税務調査に非協力だとはなり得ません。 そもそも法を逸脱した無理な調査を行おうとする調査官の方に問題がある訳ですから、調査官は文句を言うこともできないはずです。 調査官の心証が悪くなるのでは等々のご心配があるかも知れませんが、そもそも税務調査に来る調査官は性悪説、つまり納税者には必ず申告漏れがあるといった前提で調査に臨んで来ておりますので、今更心証を良くしたところで意味無しでしょう。 長いお付き合いをする訳でもありませんしね。 しかし法に基づく税務調査には全面的に協力をしましょう。 調査に応ずるのも国民の義務です。 |
| なぜ「現況調査」の様な違法な調査が行われるのか? |
| では何故明らかに違法である現況調査というものが行われるのでしょうか?。 <国税庁見解は> (納税者に)質問し回答してもらうためには、合理的と認められる場所において行うべき。対象物を五感の作用(見る聞く嗅ぐ味わう触れる)の下におくことが必要な範囲でその所在場所への立ち入りが前提となる。 この見解云々よりも、やはり税務調査を行う側の都合があるようです。 後で触れますが、調査官には年間の調査件数や増差・重加(これも後で説明)といったキツいノルマがあり、このノルマを達成するか否かが人事上の重要な査定の一つとなっているらしいです。 このノルマを達成するがためには税務調査を如何に効率的に行うかが重要であり、そのためには現況調査に成功するか否かが調査官に取って重要な事となっています。 少々法を逸脱したところで、現況調査が上手くさえいけば問題にはならない、というのが調査官の本音の様です。 事実、現況調査が上手くいって高額の脱税を見つけた、といった事例などは課税庁の内部で行われる研修会等で取り上げられ、そして調査官は査定アップとなります。研修会で取り上げられるという事は、この現況調査オンリーといった調査法が課税庁内部で推奨されているという訳です。 |

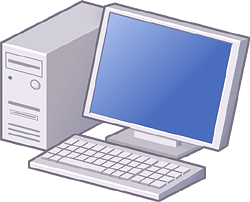
| 修正申告書の提出という行為について |
| 課税庁は調査結果について修正申告書の提出を勧奨してきます |
| 上に書きました通り、納税者側が調査官の指摘に対して修正申告書を提出すれば税務調査はすぐに終わりますし税額もその時点で確定いたします。 これがもし納税者側が調査官の指摘に不満で修正申告書の提出に応じなかった場合、課税庁側は大きなリスクを背負い込む事となります。 納税者が自主的に修正申告書の提出を行わなかった場合には課税庁は「更正決定処分」により追加の税金を賦課決定しなければなりません。その場合には税金を賦課決定する根拠となる事実と法的根拠と課税理由の立証責任が課税庁にあることから、課税庁はその税金の決定理由を文面で立証しなければならず、課税庁に取っては大変な事務負担となります。 もし処分理由の文面が不充分ならば、更正処分自体が無効となって取り消される事もあり得るという事で、課税庁側はこの文面の一字一句に充分気を遣う事となります。 またこの更正決定処分について納税者側が不服申立をしてきた場合は、国税不服審判所、更に裁判所と課税庁側の課税処分の是非が争われる事となります。 これは課税庁側に取ってみれば面倒なだけの業務であり、出来るならば避けて通りたいというのが本音らしいです。 このため、調査官は調査対象者である納税者から何としてでも修正申告書を提出させようとします。課税庁とすれば納税者が自主的に修正申告書さえ提出してもらえれば課税理由の立証責任も義務も無くなり、大幅に肩の荷が下りる訳です。 納税者にすれば、自主的な修正申告書を提出しても、更正決定を受けても納める税金に差が無い以上は、無理して調査官の指摘に応ずる必要が無い訳ですから、調査官は正に飴と鞭を使って納税者に頼み込んできます。 ホンの数分前まで社長を相手に偉そうに話していた調査官が、修正申告書の提出を拒否した途端にその態度が180度変わって低姿勢になった光景は珍しいものではありません。 |
| 納税者に取っては修正申告書を提出するという事は、 この課税に対する不服申立権は放棄します 課税に対する処分理由の記載も不要です と宣言するのと同じ事だという訳です。 一旦、修正申告書に押印して提出をしてしまったら、上の宣言をしたという事です。 少しでも納得できない部分があるのならば、納得がいくまで課税庁と交渉しましょう。 くれぐれも押印には慎重に!。 押印をして修正申告書を提出してしまったら後戻りは困難です。 修正申告書を課税庁の言うがままに提出するということは、メリットは課税庁側にだけにあって納税者側には何のメリットも無いという事を改めてご承知ください。 |
| 平成25年分の国税通則法の改正以降は、修正申告書を提出した場合には不服申立権も無くなるといった、納税者側のリスクを説明する文書を交付する様になりました。それまでは選択肢など無しに何の説明もなく修正申告書への押印を迫られていたことを思えば一歩前進した部分なのですが、どうも文書を交付するだけで細かい説明は行っていない様です。 |
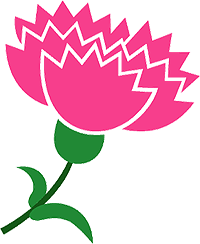
| 附帯税について |
| 附帯税には延滞税と加算税があります。 上にも記載しました様に、延滞税は追加の税金に対する金利的な性格を持つ税金であり、加算税は申告漏れ等の行為に対する処罰的な罰金という性格があります。 もし税務調査で申告漏れを指摘された場合、追加で納める法人税または所得税・消費税等の外にこの様な附帯税を納める事となります。 延滞税は追加の税金を全て納税するまでかかりますが、加算税は申告漏れという行為に対して一度だけ賦課決定されます。 |
| 延滞税 平成28年時点での割合は年2.8%です。 利率は「特例基準割合+1%」と規定されており、特例基準割合というのは毎年変わる事からこの延滞税の割合も固定しておりません。 特例基準割合は銀行の短期貸出金利を基に算定しておりますので、貸出金利が低下している平成28年時点では延滞税の割合も一番低くなっております。 (以前は年7.3%でした) なお法定申告期限から2ヵ月を経過した段階からは、この延滞税割合が9.1%と三倍以上に跳ね上がります(平成28年の場合)。 正にサラ金並みの高金利になります。 |
| 加算税 申告漏れ(または申告をしていなかった)事による制裁金と考えて良いでしょう。 追加で納税する税金に対し、決められた割合の加算税が決定されます。 【過少申告加算税】 申告漏れ等により申告済みの税金が過少だった場合、その不足税額に対して10~15%が追加決定されます。 但し税務署等に指摘される前に自分で過少申告に気付いて自主的に修正申告を行った場合には賦課決定はされません。 【無申告加算税】 確定申告期限までに申告をする義務があるのに、その申告を行っていなかった場合には15~20%が決定されます。 税務署等から指摘される前に自ら期限に遅れてでも申告を行った場合は5%です。 (例外もあります) 【不納付加算税】 これは源泉所得税の追加納税に対して賦課される加算税です。自分で自主的に追加納税を行った場合には5%で、それ以外は10%です。 【重加算税】 単純な申告漏れではなく納税者側に「仮装隠蔽」の行為があった場合、処罰的な意味から高い割合の加算税が賦課決定されます。 過少申告の場合には過少申告加算税10%に代えて35%、無申告の場合には無申告加算税10%に代えて40%もの割合で決定されます。 ※ 法定申告期限から一ヶ月以内の場合には加算税割合も軽減されます |

| 税務調査の結果に不服がある場合は |
| 上にも書きました通り、調査官が勧奨してきた修正申告書の提出にもし応じなかった場合、課税庁側は更正決定通知書という書類で追加の税金と加算税とを決定してきます。 通知を受けた納税者(企業)側は次の手順で不服を申し立てる事となります。 これを不服申立制度といい、「再調査の請求」と「審査請求」の二段階に分かれています。 |
| 再調査の請求 |
| 以前は「異議申立」と呼ばれていましたが、国税通則法の改定より名称が変わりました。 更正決定処分を受けたのが税務署の場合はその税務署長宛に、国税局の場合は国税局長宛に提出をします。 この請求申し立ては、更正決定処分を受けてから3ヵ月以内に行う必要があります。 口頭ではなく文書での申し立てとなります。 用紙は国税庁のホームページから自由にダウンロードできます。 この申し立てがあった場合、申立を受けた税務署または国税局は更正決定処分の内容を改めて担当者を代えて再検討を行う事となり、調査をやり直す事となります。 担当調査官が代わる事で更正決定処分自体が覆る事もまれにはありますが、実際には同じ役所が同じ目線で調査をやり直す訳ですから、あまり期待はできません。 この申し立てに対し、税務署(国税局)は処分結果を文書で通知してきます。 努力目標ですが、一応は三ヶ月程度で結果を出す様にしているらしいです。 「却下」・・・申し立て自体が法的に無効で門前払い 「棄却」・・・再調査した結果、原処分(最初の更正決定処分)に問題無し 「認容」・・・納税者の請求を認めて原処分(最初の更正決定)を取り消す この外に「一部認容」といって、納税者の請求の一部のみを認めて更正決定処分の一部分を取り消すこともあります。 この「再調査の請求」を経ないで直接第二段階である「審査請求」を行う事もできます。 |
| 審査請求 |
| 原則的には上記の「再調査の請求」で「棄却」または「一部認容」といった通知を受けた納税者が更に上部機関に対し不服申立を行う手続です。 原処分庁(原処分を出した官庁です)から「棄却」等の決定通知を受けてから1ヵ月以内に管轄する国税不服審判所に提出をします。 「再調査の請求」を行わないで直接審査請求をする際には「再調査の請求」同様に原処分を受けてから3ヵ月以内の提出が必要となります。 また「再調査の請求」を提出したのに、3ヵ月経っても何の回答も通知も無い場合、決定を待たないで審査請求をする事もできます。 審査請求書の提出は国税不服審判所です。 国税不服審判所は本部と全国に12の支部、7の支所があります。 審査請求書は郵送でも提出ができます。 もちろんコピー代等の細かな費用を除いて一切の手数料は不要です。 国税不服審判所は税金の裁判所です。 裁判所では裁判官に当たる審判官という人達が合議制により課税の正否を審理し、その結果である判決は「裁決」とい呼ばれ、この裁決には国税局や税務署側から不服申立を行う事ができず無条件に従わなければなりません。 原処分庁に対する「再調査の請求」とは全く違う面からも課税を検討します。 |
| 【以下、国税不服審判所のホームページより】 国税不服審判所は、昭和45年5月に国税庁の附属機関(現在は特別の機関)として設置されました。 国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関です。 この様に、国税不服審判所は一応は国税局・税務署といった課税執行機関とは切り離された別個の別組織であるとされています。 しかし双方では人事面の交流も頻繁に行われており、完全な別組織だという国側の言い分には少々首を傾げてしまいます。 事実、今までの裁決は課税庁側の課税処分を肯定する内容のものが多く、これで救済機関だと言えるのかどうか疑問視されていましたが、最近は審判官も裁判官出身者を採用したり税理士といった民間人なども登用する様になって、以前よりは納税者側の主張も通る様になった様ですが、でもまだまだ狭き門である事には違いありません。 審査請求は一年間以内に裁決を出す様にとの努力目標があるらしいです。 |
| 国税庁のホームページによれば、平成25年度に於ける審査請求で納税者側の主張が一部であっても認められたのは僅か7.7%との事です。 |
| 最後は訴訟 |
| 国税不服審判所の出した裁決にも不服がある場合は裁判所への提訴となります。 裁判所には裁決の通知を受けてから6ヵ月以内に提訴する必要があります。 審査請求までは無料ですが裁判となると手数料もかかりますし弁護士費用も発生します。 残念ながら訴訟に於いても納税者に取って狭き門である事は不服申立以上です。 これは行政訴訟全般に共通するのですが、裁判所が国の行った処分に対して取消命令を出す事は滅多にないという事実を見てもよく分かる事です。 そして税金裁判は裁判官に取っても経験が少なく荷が重いものだそうです。 司法試験に税法科目が全く無いという事から見ても、裁判官に取って税金裁判は専門外に近いものであり、どうしても国側である国税局や税務署の意見を重視してしまう様です。 |
| 「再調査の請求」と「審査請求」の手続は全て無料でできます。 ただ不服申立期間中も附帯税である延滞税だけは計算の中断がありませんから、係争期間が長引けば長引くだけ後々のご負担が重くなります。 不服な税金であっても一旦支払を済ませてから不服申立手続をされるのがお勧めです。 |


【税務調査について】トップメニューに戻る

次のページ(その2)へ